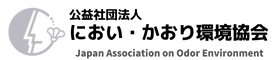日本独自の繊細な感性が生み出した
「におい」という言葉からは、「臭気」や「香り」がイメージされますが、古くは色の際立ちや美しい様を言う言葉として使われていました。万葉集でも「青(あお)丹(に)よし 奈良の都は 咲く花の 匂(にお)ふがごとく 今盛りなり」と、平城京の鮮やかに映えて見える様が「匂ふ」という言葉で表現されています。また、室町時代に確立された香道では、香りを「嗅ぐ」のではなく、「聞く」と呼びます。香木の香りを聞き、楽しむことを「聞(ぶん)香(こう)」と言います。
「香」は仏教儀礼とともに、大陸から伝えられたと考えられています。最も古い「香」の記述は日本書紀です。「香」は、奈良時代には主に仏前を清め、邪気を払う宗教的な意味合いが強いものとして用いられていました。平安時代にかけて次第に、貴族たちは日常生活の中でも「香」を楽しむようになりました。枕草子や源氏物語にも「香」の記述が多く見られます。室町時代には、武士の嗜みとして、茶道、華道とともに香道が体系化。織田信長も「香」に惹かれた一人です。天下の名香とされる香木に正倉院に収蔵されている「蘭奢待(らんじゃたい)」があり、信長が切り取った跡も残っています。
江戸時代には、町人にも「香」が広まり、香道具も作られるように。国内で初めて「線香」が作られたのも江戸初期といわれています。香りは単に鼻で嗅ぐというだけでなく、五感で感じ、生活に彩りや癒やしを与えるもの。日本の香りの文化は、独自の繊細な感性が生み出したものと言えるのではないでしょうか。