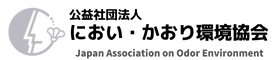令和7年5月22日に開催された公益社団法人・においかおり環境協会総会及び令和7年度第2回理事会において、会長として再任された小峯裕己です。
2016年度からの9年間に引き続き、令和9年度の総会まで会長を務めさせて戴きます。
本協会の起源は 、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭防止対策に関する調査研究を行う任意団体として、昭和44年12月に設立された悪臭公害研究会です。その後、環境省所管の法人許可を得て、社団法人臭気対策研究協会へ移行致しました。平成15年4月には、積極的に良好なかおり環境を創造し、快適な生活環境を保全するとともに、屋外空間だけでなく建築物室内空間も対象とするよう、事業内容の見直しを行い、社団法人におい・かおり環境協会に名称を変更致しました。
平成23年4月には、公益社団法人としての認定を受け、におい・かおりの環境問題全般に関して、社会的に貢献できる事業を強化致しました。
悪臭は、騒音や振動とともに感覚公害と呼ばれる公害の一種で、その不快なにおいにより生活環境を損ない、主に感覚的・心理的な被害を与えるものです。感覚公害という特性から住民の方々からの苦情や陳情と言う形で顕在化し、汚染物質等の蓄積はないものの、意外なほど広範囲に被害が広がることがあり得ます。また、見た目の汚さ、騒音や振動による不快感、高温高湿度等の劣悪の熱環境等が共存すると、悪臭苦情が増長される恐れがあります。さらに、発生源企業と周辺住民との人間関係、信頼関係なども影響を及ぼします。このように、悪臭問題は様々な要因が影響する複雑な感覚公害であると言えます。
ところで、においに関する最近の状況ですが、都市部では、悪臭苦情の対象となる事業所が大規模な工場等から焼き肉店やラーメン店等の飲食店を始めとする小規模な事業所へと移行しています。また、地方では、畜産農場における一戸あたりの飼育頭数の増加、畜産農家の存在する地域に達する住宅のスプロール化により、畜産関係の悪臭問題は深刻化するなど、いまだ課題が残されています。また、コンポストの生産施設から発生する悪臭も苦情が長期化する傾向もみられます。
一方、私達の身の回りでも、数多くのにおいに関わる問題が顕在化しています。
老人福祉施設数が大幅に増加していますが、入居者の糞尿処理に関わる施設室内の悪臭、在宅介護による介護臭等、介護者の方々にとって不快と感じるにおい環境が形成されています。
また、ペット臭、カビ臭に代表される一般家庭における嫌なにおいは相変わらず存在しています。においの原因者と被害者が同一人物となる厄介な問題です。
当該食品には通常存在しない臭気成分が付加される異臭問題(オフフレーバー)、体臭や口臭に対する過剰意識などが社会的な問題となっています。香水や、合成洗剤・柔軟剤・入浴剤・防虫剤・化粧品・芳香剤などから発散するにおいに起因して、頭痛、吐き気、アレルギー、化学物質過敏症等の症状が誘発される、所謂香害も顕在化しています。
当協会では、これらのにおい環境に関する種々の問題の解決及びかおり環境の創造に向け、従来以上に、社会から期待、信頼される事業を積極的に推進してまいります。
協会の業務を推進する上で、会員の皆様を始めとする多くの方々から、従前以上のご理解ご協力を賜れますよう、お願い致します。
公益社団法人 におい・かおり環境協会 会長
千葉工業大学 名誉教授
小峯 裕己